序盤の快進撃から少しずつ苦戦する機会が増え始めた柏、神戸川崎広島と強豪相手に上々の成績を収め昇り調子の京都。結果から言えば京都のゴールがいろんな波紋を呼んで変に話題になっちゃった試合なんですが、柏サポである私個人的には、レイソルの課題とか京都の攻撃の不思議さとか、いろいろ見所があった試合でした。ハンドのあれこれで不運だったー、で終わらせるにはもったいないのでレビューを書かねばと言う次第です。
とはいえハンドのあれこれも確かにレア事象かつ難しいルールではあるなあと調べ直して改めて思ったのでそれも解説しつついこうかなと。
ハンドを取られなかった理由について
相手チームのゴールに次のように得点する。・偶発的であっても、ゴールキーパーを含め、自分の手や腕から直接。・偶発的であっても、ボールが自分の手や腕に触れた直後に。
と書いてあります。で、この前にもハンドについて細かく書いてあるので要約すると、
「例え腕や手が自然な位置にあり偶然当たっちゃっても、直接ゴールするor直後に自分がゴールを決めたらハンドです」
という話なんです。で、柏としてはこれを元に「ハンドした直後にシュート打ったのにハンドじゃないの!?」と言ってるわけです。
今回の試合の公式記録を見るとゴールについて「オウンゴール」という記録になっています。
なので、審判団としてはゴールが直接決まったのではなく、「シュートに対して柏の選手がクリアにチャレンジし失敗した」と捉えている、なので直後に自分がゴールを決めたわけではない、よってハンドではない、と裁定したんじゃないかな?と思っています。
その上で、「あれはオウンゴールではなくシュートが直接入ったと判断すべきでは?」という意見はある。審判団によって判断が分かれてもおかしくない。
なので個人的な捉え方は「ハンドを取る人も取らない人もいるだろうからしゃーない」という結論になっています。
はい、ここがスッキリしたところで試合の中身を観ていきましょう。
はい、ここがスッキリしたところで試合の中身を観ていきましょう。
柏の2トップにした狙い、成果
柏は3421ではなく3412でのスタートを選択。立ち上がり5分ぐらいで顕著に分かるように、完全に保持を目指すというよりもロングボールによる陣地回復やカウンターを選択肢として使うための起用だと思われる。
特に細谷は今シーズン垣田木下に出番を奪われている中でのスタメン起用ということで気合いは相当入っていたと思う。
京都は前線から圧の高いハイプレスを思考するチーム、かつ3トップなので柏の3CBと数合わせは容易に出来る。そこのリスクを避けるためにロングボールの択を取りつつ保持も目指すといういいとこ取りを目指したのでは無いかなと思っていて、実際前半10分ぐらいからは保持も交える姿勢が見えてきた。
細谷が裏を取って前進しながら保持も上手くいく、という綺麗な流れのまま久保のゴラッソで先制する柏。単純にシュートが上手かった、というのはある。
京都は前線から圧の高いハイプレスを思考するチーム、かつ3トップなので柏の3CBと数合わせは容易に出来る。そこのリスクを避けるためにロングボールの択を取りつつ保持も目指すといういいとこ取りを目指したのでは無いかなと思っていて、実際前半10分ぐらいからは保持も交える姿勢が見えてきた。
細谷が裏を取って前進しながら保持も上手くいく、という綺麗な流れのまま久保のゴラッソで先制する柏。単純にシュートが上手かった、というのはある。
ただ京都の4バックに対して柏の両WBがしっかり幅を取っていたのが個人的には印象が強い。4バックはどうしても外に貼りっぱなしのWBに対して後手になってしまうので、こういった幅の使い方が出来ることは大事だと思う。
ただしこの2FWが機能したのは前半半ばまでに近く、そこからは京都が柏の狙いを制圧し始める。
26分の垣田に対する鈴木の対応を観るのが一番分かりやすいんだけど、基本的に京都は2CBがそのまま2FWをぴったり管理する形。かつロングボールで裏を取るチャレンジが出来る状況もそこまで多くなく、結果として京都の守備と柏の配置ががっちり噛み合う形に。
26分の垣田に対する鈴木の対応を観るのが一番分かりやすいんだけど、基本的に京都は2CBがそのまま2FWをぴったり管理する形。かつロングボールで裏を取るチャレンジが出来る状況もそこまで多くなく、結果として京都の守備と柏の配置ががっちり噛み合う形に。
またロングボールで陣地を回復するということは、それだけFWとそれ以外の距離が空いている状況なのでワンタッチで味方に預けられる位置にサポートが出来ない。裏を取って走れば時間も作れるのだが明確に裏へ蹴っ飛ばすシーンは徐々に減り、狙ったメリットが得られない時間が続いていた。
思ったほどロングボールのメリットを活かせず、また後述するが守備の強度的には普段より落ちてしまった部分もあり、柏としては成果を想定ほど得られなかった、という気がする。だから後半になって戻したのかな?という。
京都が保持できた理由
京都の保持に関しては説明が難しいんだけれども、ざっくり言うと
- 柏の523チックな守備に対して、2の脇にガンガン人が降りてきた
- エリアスを気にしすぎて柏のCBはマークについて行くことが難しそうだった
- 前線がプレスかけるのか撤退するのか、基準が定まらず
というあたりが大きいと思う。京都の前線は配置の偏りをあまり気にせず、ガンガン動き回る傾向にあるなーと観てて思っていて、逆サイドに張ってる人は全然居ないんだけどボールサイドは数的優位!とかが割と頻繁に起こる。
だからどこまで再現性があるかは分からないし京都ウォッチャーの方の意見を観てみるとある種運の要素が強い、というのもありそうなんだけどこの試合においては保持に対してかなりプラスに働いていたと思う。
柏の前線と中盤がどこからプレスをかけ、どこで奪うのか曖昧になった結果523気味の構えなのに保持者にプレスがかからない!という状況が起こり、スカスカになった2CHの脇へエリアス原川崎が入れ替わり立ち替わりゴリゴリとスペースを使う意識があるので結果として保持前進が実っていた。
だからどこまで再現性があるかは分からないし京都ウォッチャーの方の意見を観てみるとある種運の要素が強い、というのもありそうなんだけどこの試合においては保持に対してかなりプラスに働いていたと思う。
柏の前線と中盤がどこからプレスをかけ、どこで奪うのか曖昧になった結果523気味の構えなのに保持者にプレスがかからない!という状況が起こり、スカスカになった2CHの脇へエリアス原川崎が入れ替わり立ち替わりゴリゴリとスペースを使う意識があるので結果として保持前進が実っていた。
またそこに付いていこうとすれば機動力を活かして2列目から裏へ飛び出せるスペースも見逃さないメンツが多く、特にエリアスに走られたらまずいという意識もあった気がする。
結果として柏の守備は
「バックラインはスペースを埋めるような守備」
「前線は前からいきたい人と埋めたい人で分裂気味」
「ど真ん中のCHがなんとか埋めたり前線へ押し出すがスペースを使われる」
という形になってしまい、意図した守備はほぼ出来ていなかったと思う。だし、この状況をどこまでベンチワークや仕込みで意図したかは別として京都の攻撃陣の振る舞いは柏に対してかなり有効だった。
リアルタイムで観ていたときは「京都のサッカーってどう説明すれば良いんだろうか」と思っていたんだけど見返してみると面白い。良くも悪くも個々の判断と機動力に委ねられてる領域が広そう。ただそれでもどうにか出来る武器を各選手が持っているなと。
あとは福岡のバランスの取り方、逃げ道の作り方が非常に良くて好きな選手だと思いました。
後半の柏の修正
後半に入る際、柏は細谷に代えて仲間を投入、慣れ親しんだ3421へと戻すことに。
この交代で修正された部分は
この交代で修正された部分は
- 守備強度、特にボール保持者に対するプレスの強さ
- 京都の2CBから外れてボールを受けることによるパスの出し先の増加
- また3421にすることにより、保持を目指すという意思の統一
が大きかった。
後半すぐに迎えたポスト直撃の原川が打ったシュートも、ゴールキックを蹴らずに繋ぐ姿勢から前進を実らせたものであり、またその直前に仲間が対人守備の強さを見せるシーンが続いてたことも含め、この10分ぐらいで明確に変化が見て取れた。
保持により力を注ぐことで京都を押し込み、押し込んだところからハイプレスをかけることで簡単に攻め込ませない、もし奪えたらチャンスが作れるというところでだいぶやりたいことが見えてきた柏。
この修正による変化の大きさを観るに、改めて3421が今後主軸になる可能性はかなり高そう、というか2トップを機能させる試みはちょっと時間がかかるかもしれない、もし試すとしても木下垣田がチョイスになるのかなー、なんて思ったり。
それでも止まらない京都とエリアスの強さ
ということで、陣地の取り合いに関してはだいぶ優位気味に運べそうな雰囲気が柏に出てくるのだが、それでも京都はしっかりと陣地を取り返してくる。その要はやはりエリアス。
引いて足下良し、裏に走って良し、体を張るもよし、なんならボールを奪うのも上手い、と色んな形で時間とスペースを作れるこの人に、柏はかなり手を焼いていた。古賀が早い時間にイエローをもらったことも影響としては大きい。
また京都の運動量が落ちることなく、エリアスに対して続々とサポートで走り込む、保持者が手詰まりになったら必ず裏へ走る、という迷いの無さ。これらの動きはボール保持者の迷いを消し、速い判断でプレーを選択し続けた結果として柏のプレスでボールを奪われるシーンはそこまで多くなかった。もちろん全部が繋がるわけではなく、前線にボールを放ったところで失ったりはあるのだが、それでもリスクの低いエリアへボールを動かしておくという意味でメリットは非常に大きい。
またポジショニングの偏りを気にせず個々が動く、というのが後半半ばぐらいからよりメリットを発揮していたように私には見えた。
京都の保持前進は、スキル的に難易度の高い動作はそこまで多くない。無理な突破を目指すというよりは、前向きの味方に下げてやり直し、フリーが生まれればそこにつけるというシンプルな形。
ただポジションの偏りが発生することで、柏にはマンツーマンじゃない限り捕まえきれない選手が生まれてくる。79:30付近の画面を見てもらえると非常に分かりやすいのだが、柏のDFは捕まえる相手が居ない。
一般的にサッカーの攻撃はボール保持者に対してどれだけ選択肢を作るか、みたいなところでポジションを取るのだが京都はそれだけではない動き方が色々あって面白かった。エリアスと原はそういったファーストポジションを取るのが上手く、またその二人を観て中盤がすかさず次の動きを選択する様子は結構興味深い。
一方で逆に言えば、そこまで整理されてないアドリブ重視でもあるため、戦術的な目で京都を見続けている人は再現性がない!と嘆きたくなるのもわからなくはない。実は緻密な準備でチームとして駆け引きを仕込んでいる可能性もあり、それは試合を見ている側には分からない。あくまでこういう現象が起きてたよね、というのを観測するだけだ。
ただ動き出しが被ることや逆に必要なサポートがないシーンも時々あること、そこら辺を割り切ったボールの動かし方をしている様子などからオレはそう思った、というだけでもある。
気になるのでこれからも出来れば試合は見ていきたい。
柏の向き合う課題、細谷の今後
柏としては、ハイプレスに対してどう向き合うかというところを東京ヴェルディ戦に続いて要求される試合となった。結果として2トップが実らなかったことで、3421を軸にすることは変わらずになるのかな、という予想をしている。
一方でこの試合中に時折観られた、大きくサイドを変えてWBの確保した幅を活かすプレーはもっと増えると面白そう。特に強度高い4バックを相手にすると、どうしても幅を絞って圧縮してくるためこのプレーでスライドをさせることが大事になりそうだなと。
ただそれ以上にこの試合で見えた課題は、撤退守備の強度と試合の締め方になるのかもしれない。
試合終了間際の時間はほぼ押し込まれ、陣地回復が非常に難しかった。またチームを構成するメンツを考えても、耐久に対して適性が高いとは言えず、ここをどう凌ぐかというところ。
って思ったんだけど、そもそも論で言えばボールを持って相手を走らせることが出来なかったのを反省した方がチームとしては良い方向なのかもしれない。ここまでの試合で逆転したり綺麗に試合を締めたケースは、大半が保持に挑んで消耗させたパターンであり、またチームの構成としても今後の成長を考えてもそっち方面にチャレンジすることを選ぶかもな、と思った次第。
連戦なのでトレーニングの時間もほぼなく、戦術的な修正は難しいまま次のガンバ戦を迎えるため、もし修正できるとしたらどこまで保持を目指すかという意思統一になりそう。
あとちょっと書きたいのが、細谷について。
この試合の細谷は馬力とスピードによるボールの引き出しに関して一定の効果を見せたものの、守備の理解度と強度に課題が見えたと思っている。
垣田は守備時に細かいポジションの取り直し、背中でパスコースを消しながらプレスをかけるのが非常に上手く、また途中から投入された仲間もそのクオリティは高い。前半に守備が定まらなかった原因の一つはここにあったかもなーと。
またチームがボール保持を目指すということは、過去に細谷が担っていたロングカウンターで馬力を発揮する機会よりも、相手を背負って起点になったり短い距離でも裏を取るボールの引き出し方だったりが要求される。背負う技術は垣田に、短い距離の裏取りは木下に分がある今、細谷が自身の価値を発揮する状況が多くない、という点も辛い。
かつての柏は撤退守備で耐え、ロングカウンターでゴールを目指すことが多かった。そしてその戦術においてロングランが速く、高い推進力を持つ細谷は間違いなく軸になっていた。ただ柏というチームがFWに対して要求する仕事が変わり、適正にズレが生じているのが現状だと思う。
逆に言えば、今要求される仕事のクオリティが上がれば。
細谷は保持型でもカウンター型でも仕事が出来る万能型FWになれる。良い見本が沢山いて優秀な監督に指導されている今、立ち位置としては辛いが間違いなく今まででは得られなかった成長を遂げる貴重なチャンスだと捉えて帰ってきて欲しい。
かつてネルシーニョから構想外と告げられた柏レイソルの9番、北嶋秀朗は努力を重ねてスタメンを取り返すまでに成長した。柏生え抜きのエースなら、きっとやってくれる。
という柏サポ目線のポエムを書いたところで今回は終わり!読んでくれてありがとう!
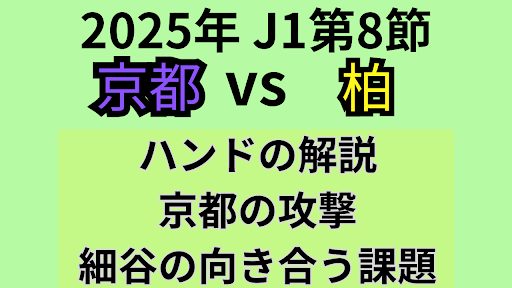






0 件のコメント:
コメントを投稿